【四柱推命】開運への道しるべ2ー用神(ようじん)とは?:「扶抑(ふよく)用神」の「扶ー水生木」について
四柱推命に於いて、自分の命式の長所、短所、又、開運時期、注意すべき時期を求めるに当たり、「用神(ようじん)」への理解は欠かせないものです。それには、先ず「用神」となる五行から考え、その五行が、どの「干支」であるかを確認し、該当する通変星の象意を検討するべきだと思います。第2回目は、「扶抑(ふよく)用神ー扶ー水生木」です。
弁天様~~~、こんにちは。
僕です。ブライアンです。
友達に聞いたのですが、「用神」を採ると、いいことがいっぱいあるんですよね。
早く、教えて下さい。お願いしま~~~~す。
ほほほ、いつも元気な方ですね。
前回、登場したスーツ姿の女性が、あなたのお友達とは知りませんでした。
今日は、彼女は来られないのですか?
へへへ、・・・僕、フライングです。
彼女との約束の時間より早く来すぎました。
まぁ、・・・・
それでは、最初はゆっくり進めましょうね。
では、ブライアン。質問ですよ。
五行に属する干支の分類は言えますか?
It’s very easy !
No problem.
| 木気 | 火気 | 土気 | 金気 | 水気 |
| 甲(陽)、乙(陰) | 丙(陽)、丁(陰) | 戊(陽)、己(陰) | 庚(陽)、辛(陰) | 壬(陽)、癸(陰) |
| 木気 | 火気 | 土気 | 金気 | 水気 |
| 寅、卯 | 巳、午 | 丑、辰、未、戌 | 申、酉 | 亥、子 |
あ、ブライアン。もう来てたのね。
弁天様、遅れてすみません。
いいえ、遅れていませんよ。
あなたを待っている間、ブライアンに、五行別「干支」を確認してもらっただけですよ。
それでは、今から本題に入りますね。
前回同様、「扶抑(ふよく)用神」について考えて行きますが、今回は「扶」=助ける方についてです。
これは、簡潔に言うと、「相生」と言うことです。
五行間の相性の良さを使う方法ですね。
日主=自星=比劫星が、命式の全ての出発点になりますので、それを例にして考えて行きましょう。
例えば、日主が「木気」の場合、2通りありますね。
ブライアン、どうですか?
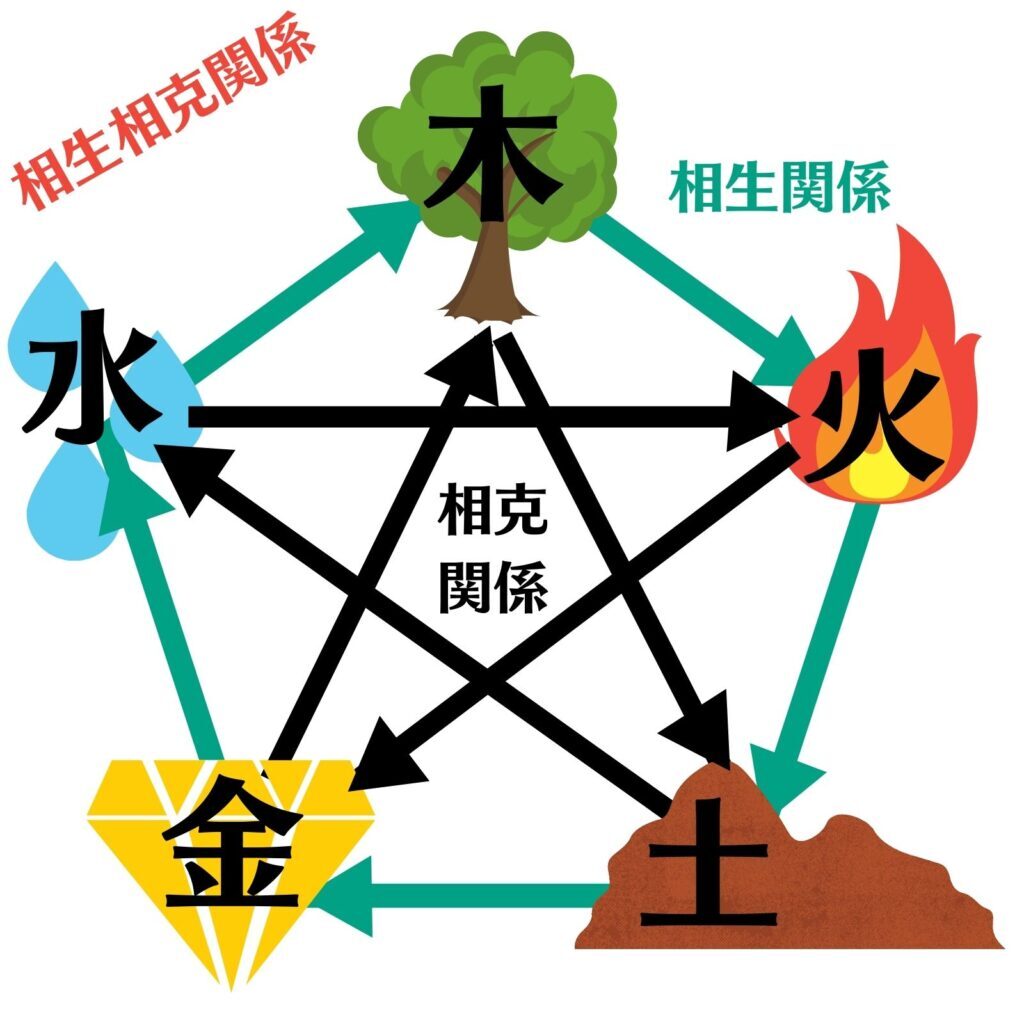

えっと。・・・
「木気」だから、「甲」、「乙」です。
それが、何か深い意味があるのですか?
はい。ありますよ。
用神の採り方として、
採るべき「五行」を決める→採るべき五行の「干支の陰陽」を決める
と言う順番があります。
今回は、命式の中で、最も重要な日主=自星=比劫星の位置を例として見て行きますよ。
それを「扶」する=助ける用神の採り方です。
通変星で言うならば、「印星」の位置ですね。
日主=自星=比劫星が、陽干であるか陰干であるかによって、扶抑用神の「扶」である「水生木」の採り方が、少し違います。
えぇ、・・・・?
どちらでも良いように思えますが。・・・
それには、理由があります。
日主=自星=比劫星の力量によって、「身旺」、「身中」、「身弱」の3タイプがありますね。
その観点から見た場合で考えてみましょう。
身旺、身中の場合、「水気」は、何が相応しいですか?

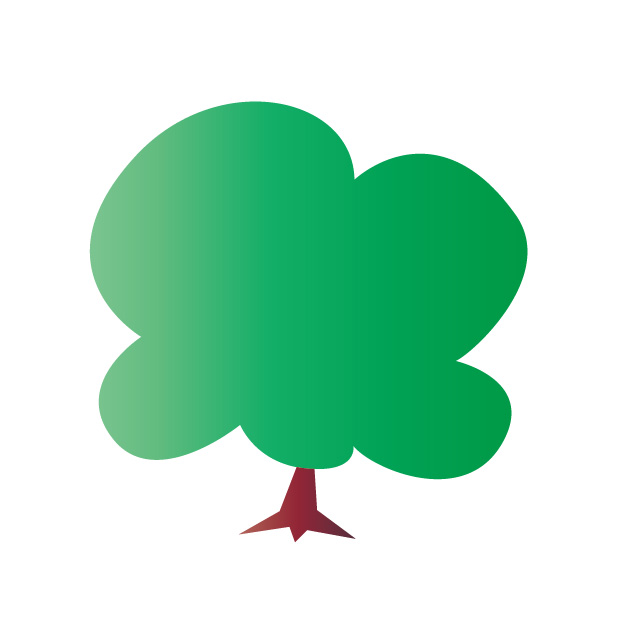


木気の「甲」は、木のイメージなので、水気2つを較べると、「癸」の方がいいと思います。
「雨」は、木に絶対必要です。
「壬」の「海」は、水分量が多すぎる気がします。
御名答ですよ、ブライアン。
「癸」>「壬」です。
「身旺」、「身中」の方なら、「壬」、「癸」の、どちらでも構いません。
でも、出来る事ならば、やはり「木」を育てるには、「癸」の方が適しています。
この場合、通変星で言うと、
日主=自星=比劫星が、「甲」だと、「癸」は「印綬星」
日主=自星=比劫星が、「乙」だと、「癸」は「偏印星」
になります。
過度の「壬」が来ると、「木」は流され、浮いてしまいます。
この状態になる事を「浮木(ふぼく)」と言います。
日主=自星=比劫星が、「甲」だと、「壬」は「偏印星」
日主=自星=比劫星が、「乙」だと、「壬」は「印綬星」
になります。
では、「身弱」の方なら、どうですか?
「身弱」ならば、日主=自星=比劫星の力量が小さいので、弁天様の御話から
「癸」しか無いように思います。
そうですね。
本来ならば、扶抑用神では無く、「通根(つうこん):今回の場合、四柱の地支に、寅や卯が来ること」が望ましいのですが、・・・
話を戻しますが、扶抑用神で言えば、やはり「癸」ですね。それが中々、採る機会が無ければ、「壬」でも構いません。代用的な扱いになり、もし金気=官星があれば、「通関用神」的な働きをする事もあります。
けれども、「壬」の水気が強いと、日主が「癸」の方は、日主が「甲」の方よりも、更に簡単に根が流されてしまうので、より注意が必要ですね。
この場合、水気の干を通変星で言うと、身旺、身中の方と同じ配置になります。
日主=自星=比劫星が、「甲」だと、「癸」は「印綬星」
日主=自星=比劫星が、「乙」だと、「癸」は「偏印星」
日主=自星=比劫星が、「甲」だと、「壬」は「偏印星」
日主=自星=比劫星が、「乙」だと、「壬」は「印綬星」
になります。
うわぁ~~~、大変だ。
弁天様の解説を聞いていて、分かった事ですが、扶抑用神の「扶」の「水生木」でも、単に「五行」だけでは無くて、「干支」まで見ていかなければならないんですね。
他にも、注意点はありますか?
「水気」が「木気」に相生すると言っても、水気の「壬」、「癸」が、天干に来るのか、地支に来るのかによって、表面化してくるスピードが違います。
相生の効果が、直ぐ表面化し易い「天干」に来るのか、継続性のある「地支」なのかと言う事も覚えておいて下さいね。
また、その「水気」の大きさも問題です。
ほんの少しなのか、大きく来るのか、と言う量的な違いも考慮する必要があります。
例えば、大運も歳運の巡りで、干や支の蔵干が1つだけなのか、両方合わせて3つや4つとなるのかも見なければなりません。
では、最後の質問ですよ。
「水生木」は、干が来る場合、「壬」、「癸」とすぐ分かるのですが、「支」が来る場合の注意点はお分かりになられますか?
へへへ、・・・簡単で~~す。
「水気」の蔵干を持っている支ですね。
多い順から言うと、「子」、「亥」、「丑」、「辰」、「申」で~~~す。
あら、ブライアン。
それに加えて、「北方合」と「三合水局」にも注意しなくてはいけないわ。
命式に「子」、「亥」、「丑」がひとつかふたつあって、大運、歳運が巡って、「北方合」になったり、ひとつだけか全く無くても「北方合半会」が成立する場合だってあるわ。
また、「子」、「辰」、「申」がひとつかふたつあって、大運、歳運が巡って、「三合水局」になったり、ひとつだけか全く無くても「三合水局半会」が成立する場合だってあるわ。
お二人の意見を足すと、パーフェクトな解答になりますよ。
用神で「水生木」の「扶」を使うのならば、
今回は「日主=自星=比劫星」を例としてお話しましたが、
基本原則として、他の五行の通変星を用神として採る場合も同様の事が言えます。
1:「水気」の干が、陽干、陰干の、どちらを必要としているか
2:その支が持つ、水気の蔵干の中身を確認。
3:「方合」、「三合局」が成立するか否かの確認。
他にも、詳細な条件はありますが、上記の2点を押さえておけば宜しいかと思われます。
う~~~~~、大変、大変。
簡単に「用神」を見つけられないなぁ・・・・
でも、ブライアン、幸せになりたいんでしょ?
それなら、
「命式の特徴」から、用神を決定する
↓
必要とする用神の「五行」の位置=通変星の位置を確認する
↓
必要とする用神の「五行の干」は、陽か陰か
↓
必要とする用神の「五行の支」に、特殊な法則が発生していないかどうか
こうやって、順番に見ていくのが一番よ。
ほほほ、その通りですよ。
命式を読み取るのは、色々な製品に添付されている「取扱説明書」を読むのと同じ事です。
焦りは禁物です。
階段を上るように、検討を進めて下さいね。
それでは、また、お会いしましょう。

